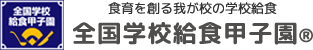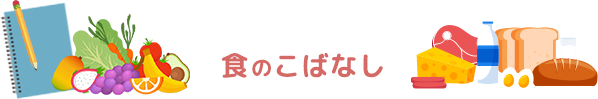


キウイ
NO.66
名前の由来はニュージーランドの国鳥
初めてキウイを食べたのは社会人になって間もないころ、先輩に連れていかれたおしゃれなレストランのデザートについていました。輪切りを半分にしたキウイは、甘酸っぱい奇妙な味の果物であり、オーストラリア産と聞いて珍しいものが入ってきたという程度の感じでした。
それが徐々に広がって、いつの間にかスーパーの果物売り場では定番の位置取りをするようになります。最近のキウイは、かなり甘くなっており、日本で栽培されるようになってから甘みが増したように感じています。
キウイは雌雄異株のマタタビ科の果実です。原産地は、意外や中国長江流域の山岳地帯でと言うことです。1904年、シナサルナシ(別名オニマタタビ)がニュージーランドに移入され、改良しながら栽培されていました。
ニュージーランドではその後、本格的に栽培して輸出果物にすることになり、それまでの英名「チャイニーズ・グーズベリー」を「キウイ」と改名されました。果実の表皮が茶色の産毛のような繊維に覆われています。国鳥のキウイに似ているので、この名前がつかられたという説もあります。
味よし香りよし色彩よしの三拍子
日本には1960年代にニュージーランドから渡来し、ミカン産地を中心に転換作物として栽培されるようになりました。茶色い表皮を剥くと、香りと共にエメラルドグリーンの甘酸っぱい果実が現れます。デザートで食べたり、サラダ、ケーキに飾りつけをしたり、ジャム、フルーツ酒に利用されるようになりました。
香り、味、色彩はフルーツの盛り合わせなどでも重宝されます。タンパク分解酵素を含むので、調理では生肉にキウイをスライスしてはさんでおくと肉が柔らかくなります。キウイゼリーを作るとき、ゼラチンはタンパク質なので、美しく仕上げるために寒天を使うそうです。
品種改良で甘い国内産が出てくる
市販されている多くのキウイは、果肉が緑色のヘイワード種が主流です。次いで2000年ころから販売が始まった果肉が黄色のゴールド種は、品種改良されたもので酸味が弱く甘みが強い種類です。その他、香緑、讃緑、さぬきゴールド、レインボーレッド、アップルキウイ、ベビーキウイなどがあります。
大きさは2~3センチと小型のキウイは、ベビーキウイとも呼ばれ、野生のコクワ(サルナシ)を連想させます。
世界のキウイの主産地は1位イタリアで、2位中国、3位ニュージーランドそしてチリ、フランスと続きます。日本ではニュージーランドからの輸入品が多いようですが、12月から4月には国内産も店頭に並び、年中食べられている果物です。日本での生産地は、愛媛、福岡、和歌山、静岡、神奈川などです。

果物の中でも食物繊維が最多
キウイは栄養の宝庫といわれる果物です。ビタミンC(アスコルビン酸)の含有量が多いこと、果実としては珍しくクロロフィルを含むのが特徴です。ビタミンCの含有量は69mg/100gで、ミカンの2倍以上でイチゴを上回ります。果物の中で最も食物繊維が多く含まれています。ビタミンE、葉酸、カリウム、カルシウム、リン、ポリフェノールも含まれています。
当分はグルコースとフルクトースが多く、酸としてはクエン酸、キナ酸、リンゴ酸が含まれ、レモン、ライムに次いで有機酸が多く疲労回復効果が期待できます。キウイの果汁抽出物について抗酸化力、血圧上昇抑制力、血栓溶解活性を試験した結果、心臓血管を保護する効果が認められています。
風邪の予防、疲労回復、美肌効果、貧血の予防、ストレスの軽減、老化の進行予防、生活習慣病予防、ガン予防、便秘改善などの効能も挙げられています。
気を付けようキウイアレルギー
キウイは、アレルギーの原因となることがある食品として表記することが推奨されています。アレルギー表示制度は、平成14年4月よりスタートしました。必ず表示される7品の義務表示品に次いで、推奨品目はキウイを含むと18品目になります。
樹上では完熟しないので、室温に放置して成熟を待つ場合もあります。サル、クマなども好んで食べる木の実です。マタタビの仲間なのですが、マタタビはネコの大好物と言われています。アクチジニンとマタタビラクトンが、ネコ科の動物に強い恍惚反応をもたらすといわれています。ネコはキウイを好んでいるでしょうか。
文:ばばれんせい 絵:とよだゆき
キウイの食品成分

出典:食品成分データベース
キウイフルーツの生産量の都道府県ランキング(平成30年)
| 順位 | 都道府県 | 収穫量 | 割合 |
| 1位 | 愛媛県 | 5,210t | 20.80% |
| 2位 | 福岡県 | 4,580t | 18.30% |
| 3位 | 和歌山県 | 2,990t | 12.00% |
| 4位 | 神奈川県 | 1,820t | 7.30% |
| 5位 | 静岡県 | 1,320t | 5.30% |
| 6位 | 群馬県 | 942t | 3.80% |
| 7位 | 山梨県 | 902t | 3.60% |
| 8位 | 栃木県 | 850t | 3.40% |
| 9位 | 佐賀県 | 695t | 2.80% |
| 10位 | 大分県 | 603t | 2.40% |
| 11位 | 千葉県 | 524t | 2.10% |
| 11位 | 香川県 | 524t | 2.10% |
| 13位 | 徳島県 | 402t | 1.60% |
| 14位 | 愛知県 | 374t | 1.50% |
| 15位 | 茨城県 | 346t | 1.40% |
| 16位 | 広島県 | 265t | 1.10% |
| 17位 | 山口県 | 161t | 0.60% |
| 18位 | 新潟県 | 154t | 0.60% |
出典:地域の入れ物
カテゴリ