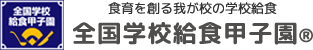「日本の学校給食」第2回 おいしくて栄養バランスのとれた「学校給食」の献立づくりと調理
子どもたちが喜んで食べ、栄養バランスのとれた、しかも安全・安心な学校給食はまず献立づくりから始まります。献立を考えるのは、栄養教諭・学校栄養職員の皆さんです。「栄養教諭」は2005年からスタートした制度で、給食管理に加えて学校での食に関する指導(食育)を進めていく教員です。学校給食の栄養士を「栄養教諭」という専門教員にしたものです。 また、「学校栄養職員」は給食管理を専門に行う職員です。2015年度は、全国の公立小・中学校に5,436人の栄養教諭と5,822人の学校栄養職員が配置されています。
給食の献立は文部科学省が定めた「学校給食摂取基準」をベースに栄養のバランスを考え、多様な食品を適切に組み合わせて作成されます。さらに子どもたちの健康状態や各地域の実情、家庭における食生活の実態なども把握しながら栄養教諭・学校栄養職員は献立を作っていきます。また、地域でとれた農産物、水産物を学校給食の献立に取り入れた郷土料理、お正月やひな祭り、七夕など日本の年中行事に合わせた伝統的な食事を取り入れているのも日本の学校給食の特徴です。
こうして作られた献立は、それぞれの地域の行政組織に設置されている「給食献立検討委員会」等で食材・調理法のバランスや安全衛生面などについて検討されて完成します。
「地産地消」の取組みも積極的に推進
献立が決まるとそれに沿って食材が購入されます。食材に関しても各自治体では、「物資購入選定委員会」等を設け、食材の品質・食味・規格・価格等を厳しくチェックして、安全で安心な食材の購入に努めています。
地元で採れた食材をその土地で食べることを「地産地消」と言いますが、日本の学校給食ではこの「地産地消」の取組みを積極的に進めています。新鮮で安全な地元の農水産物を生かした学校給食の献立を作り、昼食として提供することで、子どもたちは自分たちの住んでいる地域の自然や食文化などを学び、生まれ育った土地への愛着を深めていきます。同時に生産に携わる人々の苦労を身近
に感じて、食べ物への感謝の気持ちが育まれていくのです。

地場産物や郷土料理を生かした給食 (富山県砺波市学校給食センター、第5回全国学校給食甲子園準優勝)
古代米入りご飯、富山の幸かき揚げ、地場産野菜の炒め物、となみ野汁、
うさぎりんご、牛乳
(写真提供:全国学校給食甲子園)
そのため、多くの小学校では地元の農業や漁業を営む人々(日本では生産者と呼んでいます)と子どもたちや両親との交流を活発に行っています。農家や漁業をする人たちが野菜の育て方や魚の知識について学校で授業をしたり、また、子どもたちが実際に田植えや収穫をする体験を通して、お互いに「顔が見え、話が出来る」関係を築いています。その結果、子どもたちは給食に出された食材をより身近なものとして感じるようになり、「苦手の野菜が食べられるようになった」「給食の食べ残しが減った」といった成果に結びついています。また、地元の生産者も子どもたちに安全でおいしく食べてもらえる食材を提供するために張り切って仕事をするようになり、学校給食の強力なサポーターとなっているのです。
調理のやり方は自校方式と共同調理場方式の2種類
新鮮で安全な食材を使い、子どもたちの健康と栄養を考えた献立に基づいて学校給食は調理されていきますが、その方法は大きく自校方式と共同調理場方式(センター方式)の2つに分けられます。自校方式は学校の中に調理場があって、自校の児童生徒に給食を提供します。共同調理場方式は、複数の学校の給食を一括して調理して、それぞれの学校に配送します。一括調理は、数十食の小さな給食センターから2万食を超える大規模なセンターまでがあります。
自校方式は、温かいものを温かく、冷たいものは冷たいうちに食べてもらうという思想で学校給食を提供しており、子どもたちと調理員が身近に触れ合うメリットがあります。一方、共同調理場方式は集中管理で合理化が図れる、また総ての学校に同じメニューを提供できるので、共通の学校給食を食べるというメリットがあります。最近は少子化の影響で、学校を統合したり廃校することが進んでおり、共同調理場方式が増えています。
また、国は、学校給食の実施者が適切な衛生管理を行うため、学校給食衛生管理基準を定めており、各給食の調理施設はこの基準を遵守し、食中毒を起こさないように細心の注意を払い調理を行っています。
次回は子どもたちが給食にどのように関わっているのかをご紹介します。
文:大森光枝 (全国学校給食甲子園 事務局長)
取材協力: 齊藤るみ 学校給食調査官 (文部科学省初等中等教育局
健康教育・食育課)
なお、この記事は科学技術振興機構(JST)の中国向けポータルサイト「客観日本」で中国に配信されています。
http://www.keguanjp.com/kgjp_shehui/kgjp_sh_yishi/pt20160412141408.html
写真